|
|
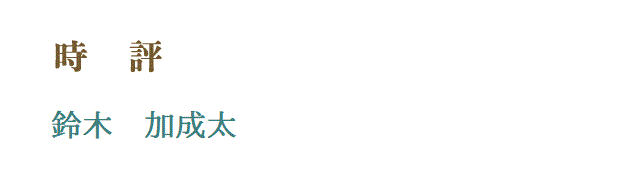 |
 |
|
|
 |
二〇一〇年代の学生短歌会やweb空間を活用した短歌コミュニティの興隆と共に登場した歌人たちの歌集刊行が近年相次いでいるが、その中には賞や選考を経て歌集刊行にたどり着いた歌人の多いことに気付く。優れた才能の多いことのほかに、歌集の刊行に直結する選考・新人賞の充実も要因にあるのだろう。
そして、結社に属さない歌人が比較的多いことの理由も、一つには、結社が担ってきた作品の選別や質の保証という役割を賞や選考も担うようになったことに求められよう。
この状況は「結社離れ」というよりも、結社の存在意義が厳しく問い直されていると形容する方が相応しい。
『はつなつみずうみ分光器』において、瀬戸夏子は二〇〇〇年以降に刊行された第一~第三歌集から、歌人一人につき一冊、計五十五冊の歌集を選び、解説を施している。「まえがき」では「ブックガイド」として企画されたとあるが、むしろ今後の短歌シーンの中で、誰のように存在感を発揮し、系譜を継ぎ、評価・受容へ至りたいのかという読者への問いかけに意識が注がれているように感じる。
「基本的に歌人は歌人=短歌を読むことに慣れている人に読まれることしか想定せずに歌をつくるが、あきらかに枡野の短歌は、短歌を詠まない人=歌人以外にもわかるように短歌をつくっている」(枡野浩一『ハッピーロンリーウォーリーソング』評より)、「こういった歌は結社系の歌人の歌集に入っていても何の違和感もない」(佐藤真由美『プライベート』評より)、「エコールに属していなかったり、大結社に属していなかったりすると、言及される機会が少なくなる」(𠮷野裕之『ざわめく卵』評より)。鮮やかな永井祐評や笠木拓評に息を呑みつつ、一方でこうした記述には歌人や結社を平面的にとらえすぎなのではないかとも思う。しかし結社の外からは結社や歌人がこのように見えており、事実そうである面もあるのだろう。瀬戸は結社の枠組みにとらわれない歌人を評価し、歌人としての在り方が多様であることを示そうとする。
不思議だねえと出会ったことをふりかえる空気のようにあなたは不思議
岡方大輔
第四十一回かりん賞は、光野律子とともに六月に急逝した岡方大輔が受賞した。「受賞のことば」での川野里子の悼辞が胸を打つ。陰日向なく同じ時間の流れの中で対等な歌人として出会い、彼らの歌や生き方と並走しつつ、その作品と生を将来へ継いでいくことができるのは、結社の長所であり続けるだろう。
短歌は選ばれた幸運な才能のためだけのものではない。この点において瀬戸の問題意識と結社の使命は限りなく親しいもののように思うのだ。
|
|
 |
|

