|
|
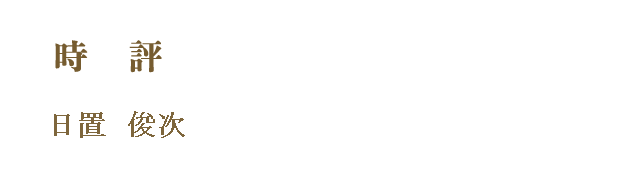 |
 |
|
|
 |
政府は水俣病被害者救済法による患者救済について、この七月で申請受付を打ち切るという。放射線被曝に似ていつ発症するかわからず、地元では問題の幕引きだという批判が強い。水俣市はチッソの企業城下町であった。企業と政府は長く無策を通したばかりか、患者を白眼視する市民も利用し、問題の封印を図った。それが被害をさらに拡大したのである。水俣病の苦しみは「銭は一銭もいらん。そのかわり、会社のえらか衆の、上から順々に、水銀母液ば飲んでもらおう。上から順々に、四十二人死んでもらう。奥さんがたにも飲んでもらう」(石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病』)という患者の悲痛な言葉に現れている。例えば「かりん」会員の桜川冴子も水俣育ちで「もはや手を隠さずともよし水銀値標準となるわれの毛髪」(『月人壮士』)と詠む。その苦しみを私はどれだけ理解しているだろうか。
思い起こされるのは、東京大学助手であった宇井純の心のこもった仕事である。一九六五年に新潟水俣病が発生し、告発を開始した彼はいわゆる「万年助手」に据え置かれて苦労した。宇井は産学協同の分野で、大学が常に企業や政府の側に立ち、被害者側の視点が欠落している事実を指摘している(『公害原論』)。
古河鉱業の足尾鉱毒事件以来繰り返される過去の公害の事例から、私は学ぶべきことを学んでいない。しかしいかに忸怩たる思いをここで吐露しても、話は進まない。
後に立命館大学名誉教授となる安斎育郎は、東大の原子力工学科一期生で、原発の危険性に気づいて批判を始めた学者である。彼は東大時代の十七年間「万年助手」に据え置かれた。主任教授は研究室のメンバー全員に「安斎とは口をきくな」と厳命した。研究費も回してもらえない。東京電力からわざわざ社員が派遣されて研究を監視されていた(「『村八分』にされ助手のまま」「朝日新聞」二〇一一・五・二〇)。九条の会を始め平和運動にも深く関与してきた安斎の原発批判は一貫しており、傾聴に値しよう。
京都大学でやはり「万年助手」に据え置かれた小出裕章は、かつて人形峠のウラン鉱害問題に取り組んでいた。無用なウラン鉱床から放置されたウラン残土により、被曝する住人が続出したのである(小出裕章・土井淑平『人形峠ウラン鉱害裁判』)。
行政や企業は、公害の対策を考えるより裏工作で逃れようとする傾向が強い。社会情勢を見通す眼を持つことは難しいが、ほんの少しでも、見えないものを見定めるように私は努力し続けていたい。理で割り切るのではなく、常に草の根に寄り添うあの「万年助手」たちの眼差しで一歩一歩、非力な歌を詠み続けていきたいと願うのである。
|
|
 |
|

